![]()
Rosa Menkman の論文和訳
テクノロジーの進化 = 不遇なドグマ
始まりは静かだった。人間がテクノロジーを生み出してから、最初のノイズは生まれた。
アーティストはまずセルロイドを引っ掻き、焼き焦がす(A Color Box by Len Lye, 1937)ことを始め、じきにその対象となるメディアは真空管へと移り、磁石を使い歪ませる(as explored by Nam June Paik in MagnetTV in 1965)という行為へと移った。歪ませることへの欲求は物質がデジタル化されてもな留まらず、プラズマテレビに文字を焼き付け(TH42PV60EH Plasma Screen Burn by Cory Arcangel 2007)、液晶ディスプレイを破壊した( %SCR2, by Jodi / webcrash2800 in 2009)。
今日のアーティスト達は、eBayあたりでT-con boardのイカレた液晶やしょぼいCCDを買い求めているだろう。
これらの作品に共通項は少ない。だがこれらは皆、エリート主義と、執拗に進化を求める現代カルチャーによって作られた被害者のドグマを示している。
消費者はチャンネルをひねりさえすれば、最新の家電製品でコンテンツを観れ喜んだり悲しんだりすることができる。これからの未来はもはや、デバイス自体に対しては今以上に興味をもたなくなっているだろうが同時に、それらが陳腐化するのももっと早くなるだろう。
完璧なる透過、完璧にインターフェースを隠そうとする欲求は、コンピューターシステムをより複雑化させ、一層入り込めない時には完全に閉じたものへと進化させていった。
曖昧なプロトコルの層から成り立つシステム、その起源とは何かと考えてみると、イデオロギー、経済、政治的ヒエラルキー、社会的慣習に見出すことができる。
ここで言う「改善」とは、「適切なプロトコル」以上のものではない、ということを認識しなくてはならない。すなわちそれは、消費者達に盲目的に信じ込まれている、完璧を究極の目標としている「進化」という名の神話である。今後一切のテクノロジーは、その不完全さの内にのみ個性を持つことになり、私はそれを「ノイズアーティファクト」と呼ぶ。
![]()
ノイズアーティファクトのアート
情報理論におけるノイズとは、特有の、ルールとさえ言える決まりを持っている。理論上、デジタルでのノイズはグリッチ(不具合)、エンコード/デコード(デジタルでは主に圧縮のこと)、フィードバック(ハウリング)に分類される。アーティストはこのようなノイズを収集して、メディア各々の特有を持った作品を作る。
■Gijs Gieskes in Sega Mega Drive2(2007)![]()
■botborg‘s Live at Ars Electronica Festival Video(2007)
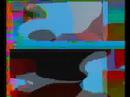
これらの作品から明らかなように、ノイズが意味することは理論で説明されている以上に複雑である。受け取り方によって意味するところが異なるからだ。
ノイズの語源は、嵐や雷、海のうなりなど、自然による攻撃、警告、大音量の現象にある。社会学やアートの文脈で探ってみると、ノイズという言葉は様々な意味で使われている。
時に、受け入れられない音を表すこともある。音楽ではない音、不正な情報、メッセージではないもの、など。またしばしば、まともなデータに対する望まれざる、求められざる、要求されざる擾乱、破損、介入を表すこともある。
しかしそのネガティブな定義が、真逆の、基準、規制、善良、美などポジティブな結果をもたらしもする。デジタルテクノロジーを分解し破壊するアーティストがいる。彼らはコンピュータを用意された正しいフローで使わず、その境界の上で遊ぶ。むしろ破壊行為がよく映るための前振りとして、観客にあえてコンピュータの本来の動きを見せることすらある。
結果、観客は、コンピューターがいかに便利さのために閉じて使われているかを知ることになり、また、本来はもっと様々な方法で使うことができるということを知ることになる。
デジタルノイズのアーティファクトはこのパラドックスの中に存在する。ネガティブを定義する一方でポジティブも再定義してしまう。
テクノロジーの正規のフローから逸脱するノイズアーティファクトは虚無を生み出すが、それはただ単に意味がない物というわけではない。観客を従来のテクノロジーのしきたりから引き離し、意味を考えさせるということを強いる。虚無でありながらも、アーティストはデジタルメディアを批評することができるし、観客にデジタルメディアの裏にある決まりごとを露にさせる。
だから、多くの人がノイズアーティファクトに対し事故的なネガティブな印象を持っているが、私は、不完全さと、新たらしい機会というポジティブな面こそ強調されるべきだと考えている。
従来機械の持つ政治、社会、経済が破綻させられた作品を見て、観客はそれぞれに固有のパターンがプログラムされていたことに気づく。
![]()
![]()
グリッチ vs グリッチアート
物体が正常の形から離れ、意味が崩壊した状態に向かっていく。初めて遭遇したグリッチは、まさに圧倒的な妨害であり、喪失、畏怖、衝撃が、手を伝わって体験された。だが一度その崩壊を体験すると、なにか希望のような感覚も現れてくる。正常と欠陥の間にある、マシンやプログラムの本質、システムが自分自身の構成を暴露しているような状況が、ネガティブな感覚によって作られる。まるで祝福されているかのように、崩壊は、私に何か新しいものを生ませてくれる創造力のみなぎりをもたらしてくれる。
ここで疑問が湧く。これは何なんだろう。どうやって作られたんだろう。グリッチ?か?
しかし、一度グリッチと名づけると、それはもはやグリッチとしての威力を失い、新しい形が突如として目前に現れる。グリッチには決まった形や状態はない。予想外な、アブノーマルな操作として知覚され、システムにおける破損である。
しかしその現象がグリッチと名付けられ、認識され理解のされ方が変化していくと、それに伴ってグリッチ自体の均衡も変化していく。発見時に感じられた崩壊の感覚は勢いを失い、新たな状態の中に消え去ってしまう。新らたなモードとなり、最初の発見は、個人的な束の間の体験として置き去りにされる。まさに「ノイズ」のように、「グリッチアート」という言葉における「グリッチ」は、比喩的な意味で使われており、「グリッチ」単体で意味するものとは若干異なる。グリッチアートの分野は、天候のようにうつろぐ。穏やかだと思ったら雷が起こるように ・・略・・(グリッチアートの劇的さについて形容)
従来のプロトコル(:慣習、決まりごと、のこと)を砕いて新しい物を生み出すために、グリッチは、ノーマルとの間にある薄皮を頼りにしている。パーフェクトなグリッチは、破壊によりどれだけオリジナルを変化させたかを示す。ひとたびグリッチが新しい表現方法、新しい言語と見なされ理解されると、転換点(tipping point)は過ぎ、グリッチとしての本質は消失してしまう。そのときはもはやグリッチは拒絶のアートではなく、新しいアートと見なされてしまっている。グリッチに携わるアーティストは、このような脆い平衡状態を捉えることを目指している。彼らは新しい形が生まれるポイントを探し続けている。
![]()
![]()
ホット・グリッチ,クール・グリッチ
グリッチアートの本質というのは、従来のアートのそれとは異なる。とある瞬間にショッキングな体験、感覚として得られるグリッチだが、未来にそのままその感覚を保存し続けることはできない。
coolなグリッチによる美しい作品は神秘的であり偉大である。アーティストとして私は、ランダムで美しく、崩壊したユートピアを求め、不確実なバランス、うつろい、掴めず認識できないものから来る何かを捕らえようとし続けている。
グリッチアートの本質は、このように「うつろぎ」の記録として、崩壊発生の仕方にあるように理解される。フォーマットのない「手続き型のアート(procedural art)」であるということである。
しかしながら、これまでの私のグリッチ作品は、私個人的な原型として作られていったという事も言っておく。アイディアのサンプル、もしくはモデルであるように感じてきた。
また、グリッチの、グリッチまでの過程という本質を全く重要視しないアーティストが存在することも知っている。
彼らは、破壊→創造の過程をスキップする。そして、最終的な製品としての形のみを目指し、最新のグリッチをいじってみたりして、デザインという点にのみフォーカスする。
これは、プラグイン、(:映像系ソフトでいう)フィルター、もしくはグリッチさせるためのソフトウェアとみなせ、自動的にグリッチを引き起こすまるでエフェクターである。とある想念に則って得られたアイディアの(意訳:他人のアイディアに則った)サンプルもしくはモデルであるグリッチアートもあるということだ。
こういった’保守的グリッチアート’、’hotグリッチアート’は、制作過程にではなく、デザインと、最終的な作品としての形にフォーカスしている。
これについて異議を唱える。
デザインのためのグリッチとは、グリッチを飼い馴らすということだ。ツールか何かで制御されたグリッチは、もはや本来の力を失っており、予期できるものになってしまっている。
もはやテクノロジーの破壊や暴露ではなく、養殖である。多くのものがすでにグリッチではなく、プリセットもしくはデフォルト状態のフィルター(:ソフトウェアのエフェクターのこと)だ。
かつてグリッチだったものは、新しいコモディティになってしまう。
このようにグリッチアートが常にパワーを持っているというわけではない。多くの作品はすでに転換点(tipping point)を過ぎてしまったものであるか、もしくは最初からそこに到達していないものである。グリッチアートは、製造と承認という、2つのシステムの間で成り立っている。グリッチアートの作品についての当事者(:責任を負っている人)は、アーティストだけではない。外部からの入力(文法的に誤ったエンコーディング)、(狙いどおりに?データが衝突するような)ハードウェアやソフトウェア、オーディエンス(デコードする人であり、つまり承認する人)など、全てが責任を負っている。
作品が最終的にグリッチアートとして成り立つためには、異なる環境にあるこれら全てが関与している。
エラーが故意によるものだとしても、他人からするとそれがグリッチだと思わすことができるのは、これが故である。また、グリッチアートが常にショッキングに感じらるわけではなく、また多数の要素に依存した表現分野として見なされるのも、これが理由である。グリッチアートの作品は、このように、様々な関係者の知覚、理解の集合に基づいている。
したがって、(注釈:論旨がこの結論に達した事が面白いが)グリッチ本来の力を失った、もしくは最初から持っていない製品であっても、それらをグリッチアートの領域から排除することはできない。
事故的な、まさにアバンギャルドなものが大衆化されていってしまうのは避けられない運命にある。だとしても、グリッチアートがよく結び付けられるテクノロジーの民主化、自由というようなファンタジーなユートピアと、上述のホットグリッチアートデザイン、グリッチフィルターとの間には、何の関係もない。テクノロジーの自由というものがあるのだとすれば、それはクールグリッチアートにおける、グリッチがまさに規則を頼ろうとする(意訳:既成の規則を崩すために)その過程にのみ、存在するのだろう。
![]()
![]()
アクーマスティック・ビデオスケープ
普通に(グリッチさせずに)テクノロジーを使う時私は常に、機械を一方向からのみ見るようにしている。できるだけ早くテクノロジーの使い方を理解したいときは、そのインターフェースや部品の構造などは一切興味持たないようにするということを学んだ。そこで私がグリッチを引き起こしてみると、テクノロジーは元あった難解な箱の中に戻っていく。機械は、内部の動作を壮大なベールの下に隠している。私は、元々の本来の姿を知らないままにグリッチを引き起こしている。そうすることで、構造の解釈や、実際に目で見えている部分以上のことを、私やオーディエンスは知ることができる。一例として私の作品 Radio Dada(2008) がある。オーディエンスが観たり聴こえてたりしたものについての議論の後に、テクノロジー的にはこういうことが起きていたんだよと、この作品を見せることで説明したい。
■Radio Dada of Rosa Menkman

Radio Dadaのグリッチは、Acousmatic Videoscape( = 機械を通してのみ生成される映像)を形成している。そこで私は、自らの視力で感知できる以上のものをついには感じ取ることができた。悠々としたそれはユートピアへの入り口のように思えるが、同時に、私がそれまで知っていたテクノロジーを破滅させうるブラックホールのようでもある。制作した Acousmatic Videoscape ではトランスメディアな美学を用いて、自らリラックスし、自らに批判的で、自らを表現するテクノロジーについての、人間の考えを理論化した。私は共感覚(synesthesia)を、単なるメディアからメディアにコードを移すという方法ではなく、コンセプト的に分離された映像と音声が合成されるという方法として、未発見なテクノロジーの領域で発見することができた。
![]()
![]()
クリティカル トランスメディア・エイセティクス
ソフトウェアを用いたアートにおいて、グリッチはしばしば進化という神話を破壊し、完璧なるテクノロジーの追求を阻止しようとしてきた。そこでは、通常は欠陥として拒絶される物体が強調されており、また事故やエラーが新しい形として迎えられていた。グリッチは、作者だけでなく機器やメディア、ツールの死を引き起こしてきた。
「アート史とは、異なる質の、新旧の文化が連続して構成しているのだ」と考える人達に対し、グリッチの破滅的な様式は問題を提起する。アート史家は新旧のギャップを埋めるのに、繰り返し新しいジャンルやメディアの形を作ってきた。
その結果どうなったか。データベンディングやデータモッシング、サーキットベンディングと言った多数の言葉が作られたが、しかし実際これらは、プラットフォームが異なるだけで、不具合の起こり方はそっくりだと言える。
理論家も同じ問題に当たった。彼らの場合は、ポストデジタルやポストメディア美術といったような言葉を使って、これまでは上手く解決してきた。だが不遇なことに、これらの言葉は誤って受け取られてしまうように思える。なぜなら、「ポスト」というのは、以前の形態に対しての反応する事を意味するからである。なおかつ、何かに対し反応する、ということは、その何かから完全に離れることを意味してはいない。実際、反応するという事は、少なくとも参照される事があるわけで、その意味で反応される側は延命される事になる。このアート史家、理論家双方の問題を解くためには、グリッチアートを、複数メディアに対峙しつつ複数メディアの領域における、「手続き型」のアクティビティと見なすべきではなかろうか。
私はこれを、クリティカル・トランスメディアエイセティクスと呼んでいる。ここにおけるグリッチの役目は2つある。一つは、この美学は、メディアが瀕死の状態(破滅し、望まれていなく、認識されず、事故的で恐ろしいげな状態)であることを示す。この美は、消費者が正常と感じることを変形させ、ティッピングポイント(転換点)を過ぎた事を告げる。この転換の後、メディアはおそらく新しい何かに変化する。
もう一方、この美は、メディア自身のジャンル、インターフェース、期待されているものを批評する。受け継がれてきた指針や、培ってきた創造のための順当法に対し、挑戦をする。
![]()
グリッチスピーク, グリッチスタディ
「狂わない理由はない」とFoucault が言うように。「カオスなしでは秩序は存在しえない」とGombrich が書いたように。また「テクノロジーの進化とはそれ自身が抱えているアクシデントなしではありえない」とVirilio が言うように。
私は、秩序とは妨害なしでは理解されず、グリッチなしでは機能しない、と考える。グリッチを学ぶのはそのためだ。グリッチをテクノロジーと見なす人もいれば、社会の構造と見なす人もいる。私は、あるひとつの感受され方を他のそれの上に置くことは無意味だと考えている。グリッチスタディは、その中間、その両方で、どちらでもなく、またその両方を超えたものだ。グリッチは人間の感覚を超える以上の物ではない。10年前にグリッチであったものの多くは、今やもうグリッチではなく、フェティッシュ向けなレトロなコモディティと化している。物質がメディアの構造、操作性、機器に支配されているような不安定な状態にグリッチは存在する。グリッチの物質性は作品が現れる機器にあるのではない。グリッチが拠り所としている、常に変化し続ける社会との文脈、美学と経済のダイナミクスといった構造の中にこそ、存在している。そしてそれはもちろん、多様な関係者達がそれぞれ意味を作り出すことが可能だという観点からである。
グリッチスタディでは、ナンセンスと知識のバランスを取ろうとしている。それはグリッチスピークや新しい表現のボキャブラリー、進化し続けるデジタルのカルチャーを通じてなし得る。これらの表現は、言語の範疇、言語を推定すること、そして言語を期待するということをスピーカーに教える。何を言うべきでないか、何を除くべきか。
グリッチスタディでは、既知な事象を未知な物に解体しようとする一方、未知を探すこともする。何が受け入れるべき姿勢で、そうでないものは何なのか、何が範疇外なのかを示してくれる。グリッチを捕らえ説明することは必要悪であり、新しい思想と行動を生み出すことに繋がる。もしその新しいモードが標準化されれば、グリッチスタディはフォーカスと趣旨を、新しいテクノロジーや論説に関するその時点でのアウトサイダーを見つけ、そこにシフトさせる。
グリッチスタディとは、場違いな真実である。それは、自身による選択と、忘却のために、自身を崩壊させるということである。最良のアイディアは、覚醒を生んでしまうことになり、つまり危険なのである。
グリッチスタディとは、別に関わる必要はない、無視できるものである。
Back


